- 電話相談/最短30分でお迎え -
- 前もったご相談/ご準備を -
- 事前の請求で最大30.5万円割引 -
ご危篤/ご逝去で
お急ぎの方へ
最短30分で
お迎えにあがります


通話料無料・24時間365日対応
2/13(金) 16:25 現在 最優先で対応可能
ご不安な時間を少しでも短くするため、
深夜/早朝でも、すぐお電話・対応が可能です

ご不安なときは、まずは状況をお聞かせください。八王子市(長沼・北野・打越町・片倉町・大和田町)周辺でご葬儀をお考えの方が、最初に迷いやすいのは「どこに連絡するか」「何を準備するか」「費用はどれくらいで、相続でどう扱われるか」という点です。
本稿では、結論から順に「税での扱い」「申請の手順」「保存すべき書類」「費用を抑える考え方」を整えました。そもそも、何を考えれば良いかわからない方が大半です。ご意向や状況をお聞きの上、最適なご葬儀をご案内いたします。
結論として、所得税では原則として葬儀費用は控除されません。一方で、相続税では被相続人(お亡くなりになった方)に関する葬式費用が「債務」として遺産から差し引ける場合があります。
また、自治体の葬祭費補助金は、東京都内(例:八王子市)では多くの場合非課税の扱いです。具体の金額や要件は自治体ごとに異なるため、最新の情報をご確認ください。
| 税目・給付 | 扱い |
|---|---|
| 所得税 | 原則控除不可(私的な支出に当たるため) |
| 相続税 | 葬式費用は「債務控除」の対象になり得る |
| 自治体の葬祭費補助金 | 多くは非課税扱い |
所得税の控除は、主に「所得を得るために必要な支出」や「社会保険料・扶養」などを対象に設計されています。葬儀費用はご家族の私的なご負担と位置づけられるため、一般的には所得控除の対象にはなりません。
ただし、事業主さまが業務上のしきたりとして用いる弔慰金や香典など、業務に関連する特別な支出は例外的に経費と認められる可能性があります。特殊な事例は税務署や税理士へ事前にご相談いただけると安心です。
相続税の申告では、被相続人に関する債務が遺産から差し引かれます。社会通念上、ご葬儀に直接必要と認められる支出は「葬式費用」として整理され、控除の対象になり得ます。第13表(相続税申告書の内訳)に明細を記載し、領収書や請求書などで支出の実態を示すことが大切です。
お布施などで領収書が出ない場合は、日付・金額・支払者・受取人などを明記した支払メモを残し、できれば受取人や関係者の署名を添えて補完しておくと安心です。
| 控除されやすい例 | 控除されない例 |
|---|---|
| 通夜・告別式の会場費(斎場/葬儀を行う部屋の使用料) | 墓石の購入費 |
| 火葬料 | 仏壇・位牌の購入費 |
| ご搬送費 | 四十九日以降の法要費用 |
| 祭壇や生花の費用 | 香典返しの費用 |
| 僧侶へのお布施 |
ご心配なことは、私たち「家族葬の四季風(しきかぜ)」が、いまのご事情に合わせて道筋を一緒に整えます。相続税の第13表の書き方や必要な書類の整理もお手伝いできます。まずはお電話でお話をお聞かせください。0120-22-5940
八王子市の国民健康保険などに加入されていた場合、葬儀を執り行う方が「葬祭費補助金」を申請できることがあります。金額は東京都内では5〜7万円の範囲が多く、要件や必要書類は自治体により異なります。提出前に、八王子市の公式情報で最新の要件をご確認ください。
一般的に準備される書類の例は次の通りです(地域により写し不可など運用が異なることがあります)。
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)に加入していた方は、「埋葬料(費)」の支給対象となる場合があります。葬祭費補助金と埋葬料(費)は、同時に受け取れないのが一般的です。
処理期間は自治体や時期により異なりますが、数週間から1〜2か月程度が目安とされることが多いです。混み合う時期や書類の不備があると長くかかる場合がありますので、提出前に必要書類の最新要件をご確認いただけると安心です。
書類や要件は状況によって異なります。「この書類で足りるのか」など、迷われたらお電話でご相談ください。お話を伺いながら、必要なことの一覧を一緒に整えます。0120-22-5940
相続税申告や自治体の手続きで確認されることがありますので、領収書は原本で保存し、日付順にファイルしておくと安心です。
お布施などの現金支払いで領収書がない場合は、支払メモ(日時・金額・支払者・受取人・内容)を作成し、可能であれば受取人の署名を添えてください。ご家族の間で立て替えた費用がある場合は、負担割合を書面で合意しておくと後の行き違いを防げます。
費用を抑える基本は「内訳を比較する」「公的給付を活用する」「ご葬儀の内容を見直す」の三点です。まずは2〜3社で、同じ条件での書面のお見積りを取り、「葬儀費用」「斎場費用(式場の使用料/火葬料など)」を明確に分けて比較すると、どこに差が出ているかが見えてきます。
あわせて、葬祭費補助金や生命保険の死亡給付(ご契約に応じて異なります)を早めに確認し、支払い計画に見込みを立てると落ち着いて進めやすくなります。式の形式を簡素に整えることも、ご負担の軽減につながります。
八王子市(長沼・北野・打越町・片倉町・大和田町)周辺で、私たちがご案内する自社斎場では、1日1組限定で他の方の目を気にせずお別れの時間をゆっくりお過ごしいただけます。広すぎず狭すぎない、ご家族葬にちょうど良い空間をご用意しています。
私たち「家族葬の四季風(しきかぜ)」は、東京都内に家族葬専門の斎場を多数ご用意し、創業50年以上の実績があります。東京都の多くの地域で口コミ1位の評価もいただいております。安心してお任せいただける体制で、費用面のご不安にも丁寧に寄り添います。0120-22-5940
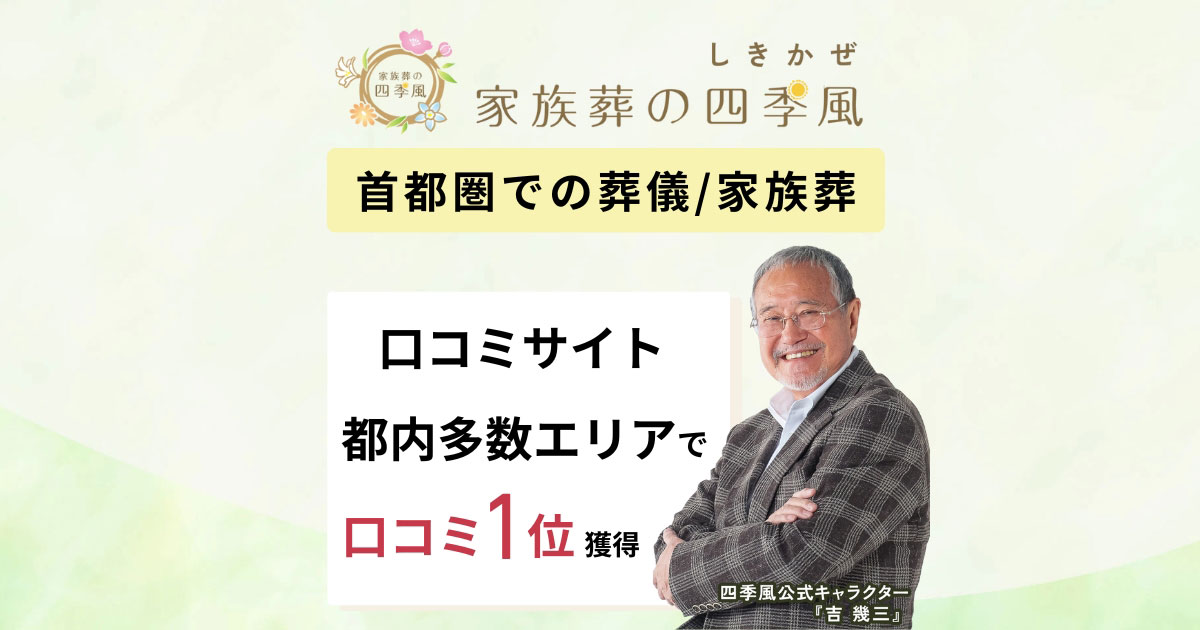
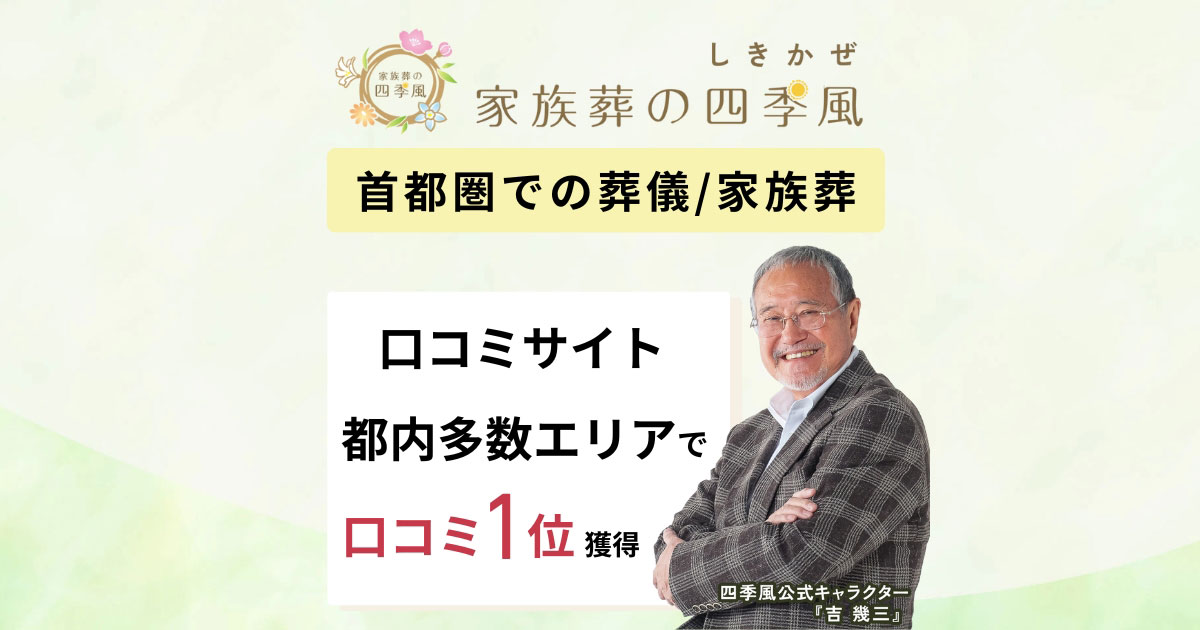
東京都内でご案内する「家族葬の四季風(しきかぜ)」の自己負担金額(すべて税込)は、葬祭費補助金の適用と会員併用時で次のとおりです。人数は目安です。
会員割引のみ適用時は、直葬火葬式97,900円〜/一日葬370,293円〜/家族葬392,293円〜となります。詳細は、葬儀プランの一覧や、各プランのページ(直葬火葬式・一日家族葬・二日家族葬)をご覧ください。
長沼・北野・打越町・片倉町・大和田町にお住まいの方には、八王子市内の自社斎場「家族葬の四季風 八王子」「家族葬の四季風 八王子 長沼」など、最寄りの斎場(葬儀場)をご提案いたします。ご親族だけの小規模なご葬儀から、会葬の多い形式まで柔らかく整えられます。
さらに詳しく知りたい方は、トップページからもご覧いただけます。
些細なことでも、まずはお聞きください。ご心配なことがあれば、私たちがいまの状況やご意向をうかがい、無理のない進め方をご一緒に整えます。0120-22-5940
長沼(八王子市)でのご葬儀費用は、所得税では原則控除の対象ではありませんが、相続税では社会通念上の「葬式費用」として遺産から差し引ける場合があります。
自治体の葬祭費補助金(東京都内は5〜7万円の範囲が多い)は非課税扱いが一般的で、申請は最新の要件に沿って、本人確認書類・葬儀を確認できる書類・口座情報などを揃えて進めます。領収書は原本を保存し、第13表の下書きや専門家への相談も視野に、落ち着いてご準備いただけると安心です。必要なときに、私たち「家族葬の四季風(しきかぜ)」へいつでもご相談ください。